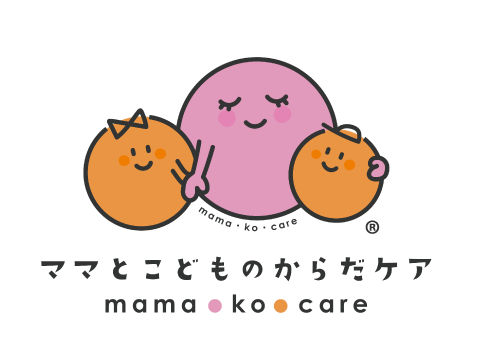目次
夜泣きとは

赤ちゃん(生後5~6ヶ月頃)から幼児(2~4歳頃)の子どもが夜中に突然泣き出し、なかなか泣き止まないことを夜泣きといいます。昼間は元気に過ごしているのに、夜になると急にぐずり、ママやパパがあやしてもなかなか眠れないこともあります。夜泣きは成長の一過程であり、多くの赤ちゃんが経験するものですが、親にとっては大きな負担になります。
夜泣きの原因
自律神経の未発達
赤ちゃんはまだ自律神経の調節が未熟で、昼夜のリズムが整っていないため。
睡眠のサイクルが短い
大人よりも睡眠の周期が短く、浅い眠りの時間が多いため目が覚めやすい。
興奮や刺激の影響
昼間に強い刺激を受けたり、環境の変化があると夜泣きにつながることがある。
空腹やお腹の不快感
まだ胃が小さく、夜中にお腹が空いたり、ガスがたまることで不快に感じることがある。
歯の生え始め
歯が生え始める時期(生後6カ月頃~)には、歯茎のむずがゆさが夜泣きの原因になることも。
成長過程による影響
ハイハイや歩き始めなど、新しい成長の段階を迎えると、一時的に睡眠が不安定になりやすい。
こんなお悩みありませんか
- ・夜中に何度も泣いて起きてしまう。
- ・あやしてもすぐには泣き止まず、寝かしつけに時間がかかる。
- ・夕方から夜にかけて機嫌が悪くなりやすい。
- ・昼間は元気なのに、夜だけぐずることが多い。
- ・夜泣きが続いてママやパパの睡眠不足が深刻になっている。
関連症状
寝つきが悪い
なかなか寝つかず、抱っこや添い寝が長時間必要になる。
昼夜逆転
夜に頻繁に起きるため、昼間に眠りがちになることがある。
情緒の不安定
睡眠不足が続くと、赤ちゃんの機嫌が悪くなりやすい。
セルフメンテナンス
生活リズムを整える
- ・朝は早めに起こし、日光を浴びさせる。
- ・昼間に適度に体を動かして遊ばせることで、夜にぐっすり眠れるようにする。
寝る前の環境を整える
- ・お風呂に入れて体を温め、リラックスした状態で寝かせる。
- ・部屋を暗くし、テレビやスマホの音を控えめにする。
夜泣き対応をシンプルに
- ・すぐに抱き上げず、トントンしながら落ち着かせる。
- ・一度起きた後は、できるだけ静かに対応し、再び眠りやすい環境を作る。
ママ・パパも無理をしない
- ・夜泣きが続くと親も疲れてしまうので、交代で対応する。
- ・家族や周囲に頼れるときは協力してもらう。
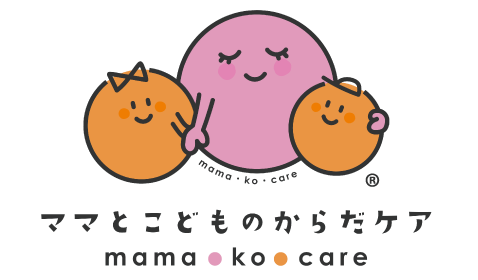
夜泣きは赤ちゃんの成長過程の一部であり、必ず落ち着く時期がきます。焦らず、赤ちゃんの生活リズムを整えながら、できるだけリラックスして向き合いましょう。ママこケアでは、赤ちゃんの夜泣きに伴うママの疲労回復やストレスケアをサポートし、健やかな育児を応援します。無理をしすぎず、家族みんなで乗り越えていきましょう。

- 監修者
- ミツカル接骨院 院長
- 𠮷原 幸治
高校卒業後、柔道整復師国家試験に合格し、1年後にははり師・きゅう師国家試験に合格。有限会社やまがたに入社後、静岡県東部の接骨院、静岡市内接骨院に勤務し学園みずほ接骨院で院長を経験後、2022年3月にMARK IS 静岡にてミツカル接骨院を開院。現在は接骨院にて接骨業だけでなく鍼灸施術、ちびっこはり(子ども向け)と幅広い施術を行う。
- 保有資格
- 柔道整復師、はり師・きゅう師、認定卒後臨床研修指導柔道整復師認定、ちびっこはり勉強会修了