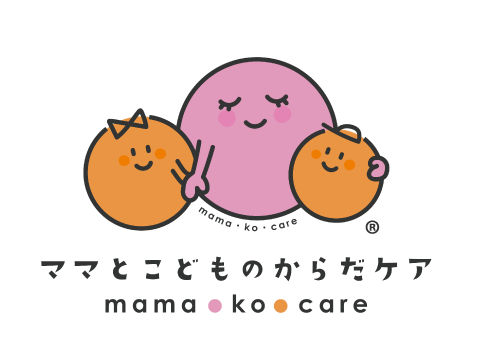目次
COLUMN
産後ママの「睡眠の質」が悪い…“睡眠障害・育児離れ”の原因とケア
「睡眠時間はとれているのに疲れがとれない…」それ、産後の“自律神経型不眠”かも?
産後のママにとって、睡眠の質の低下は切実な悩み。
「赤ちゃんがようやく寝たから自分も寝たのに、全然スッキリしない…」
「夜中に何度も目が覚めて、寝た気がしない」
このような状態が続いているなら、単なる“寝不足”ではなく、ホルモンと自律神経の乱れが引き起こす“睡眠障害”が関係している可能性があります。
なぜ産後は睡眠の質が落ちるのか?
ホルモンバランスの急変化
妊娠中に高まっていたエストロゲンやプロゲステロンが、出産後急激に低下します。
これにより、睡眠・覚醒をコントロールする体内リズムが乱れやすくなります。
自律神経のバランスが崩れる
産後の生活は、授乳・抱っこ・寝不足の連続で常に交感神経が優位な状態になりがち。
この“戦闘モード”が続くと、寝ようと思っても副交感神経が働かず、浅い眠りしか得られない状態になります。
「育児離れ不安」も関係?
近年、注目されているのが「育児離れ不安」。
赤ちゃんと離れていると不安になる心理状態が、無意識下で緊張を生み、深い睡眠に入るのを妨げる要因になります。
注意すべきサインと放置リスク
以下のような状態が1ヶ月以上続く場合は注意が必要です。
- 入眠困難(寝つけない)
- 中途覚醒(夜中に何度も起きる)
- 熟眠障害(眠った感じがしない)
- 起床時の疲労感、動悸
- 日中の倦怠感、集中力の低下
- 育児への意欲低下、イライラや落ち込み
特に、産後うつや産後不安障害の初期症状として現れることもあるため、「そのうち治る」ではなく、早めのケアが重要です。
ママが今すぐできるセルフケア
1. 昼間に“脳を休ませる時間”を確保
10〜20分の仮眠でも効果的。スマホやテレビを避け、静かな空間で目を閉じるだけでもOK。
2. 副交感神経を高める入眠ルーティン
- 寝る前の深呼吸、ストレッチ、温かい飲み物
- ハーブティー(カモミール・ラベンダーなど)も◎
3. 赤ちゃんと一緒に「休む」意識
「寝かしつけたら家事をしないと…」と無理せず、“自分を休ませる時間”も育児のうちと割り切る。
4. 生活環境の見直し
- 寝室は暗く、静か、適温を意識
- 就寝前のスマホ・テレビは控える
- パートナーとの夜の当番交代制も検討を
柔道整復師・鍼灸師 監修コメント
産後の睡眠障害は、交感神経の過緊張やホルモンの急変が背景にあります。
施術では、頭部や背部の緊張緩和、骨盤周囲の調整を通じて、自律神経のバランスを整えるサポートを行います。
睡眠の改善によって、日中の育児のしやすさも大きく変わるので、気軽にご相談ください。
ママこケアからのメッセージ
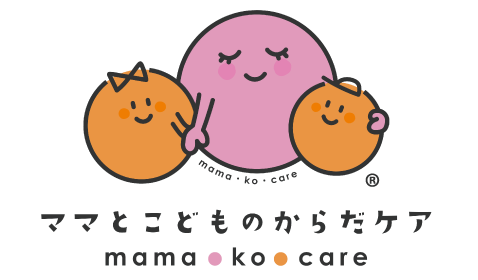
睡眠は“育児に必要なエネルギー源”です。
でも「夜中何度も起こされるのは当たり前」と頑張りすぎていませんか?
「ママが眠れない=ママのせい」ではありません。
ホルモンや環境、自律神経のバランスなど、“仕方のない要因”がたくさんあるのです。
ママこケアでは、睡眠トラブルや産後の不調に対応できる院をご紹介しています。
我慢せず、専門家に頼る一歩を踏み出してみてください。
※治療内容・方針は院によって異なります。詳細は各院にご確認ください。