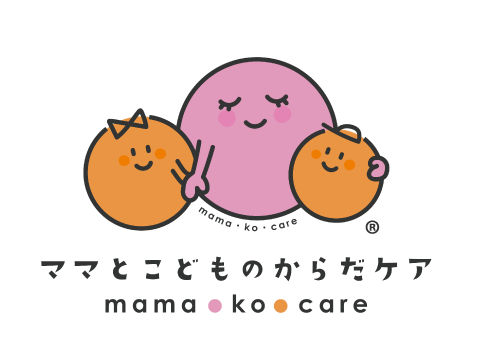目次
COLUMN
足が疲れやすい・転びやすい…“子どもの足裏アーチ”要チェック!
「すぐ疲れたって言う…」「よくつまずく」「足の裏を痛がる」
そんなお悩み、実は“足裏アーチ”の未発達が関係しているかもしれません。子どもの足は、発達段階にあるからこそ日々の習慣や姿勢、歩き方のクセによってバランスが大きく左右されます。
今回は、足裏アーチの役割・崩れのサイン・家庭でできるチェックポイント、そして整体や鍼灸などの専門的ケアについて解説します。
足裏アーチとは?なぜ大切?
足の裏には、3つのアーチ(内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチ)と呼ばれるバネのような構造があります。
このアーチがあることで、
- 地面からの衝撃を吸収する
- バランスを保ちやすくする
- 正しい歩行をサポートする
などの重要な役割を果たします。
しかし、このアーチが未発達だったり崩れていたりすると、
- 疲れやすい
- 転びやすい
- 姿勢が崩れる
- 足首や膝の痛み
といったトラブルにつながる可能性があります。
足裏アーチが未発達な子に見られるサイン
以下のような様子が見られたら、アーチの形成がうまくいっていないサインかもしれません。
- 靴のかかとだけがすり減っている
- 歩くときに足音がドスドスと大きい
- 片足立ちやケンケンが苦手
- 「かかとが痛い」と訴える(シーバー病の前兆)
- スポーツで足をすぐ痛めやすい
おうちでできる!足裏アーチのチェックポイント
土踏まずが見えるか確認
3歳を過ぎても土踏まずが全くない場合は要チェック。
片足立ちで10秒キープできるか
バランス感覚とアーチの安定性を確認。
足指でグー・チョキ・パーができるか
足の筋力や柔軟性がアーチに影響。
靴のすり減り方を見る
かかとだけすり減っていたら偏った体重のかけ方かも。
歩き方・立ち方を後ろから観察
内股・外股・ガニ股歩行はアーチ崩れのサイン。
足裏アーチの崩れを放っておくと?
足裏アーチが未発達なまま成長すると、
- 偏平足や外反母趾
- 成長期の膝・股関節トラブル
- 疲労骨折のリスク上昇
- 姿勢不良・猫背
- 集中力の低下
など、身体全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
足裏アーチは“つくる・育てる”ことができる
子どもの足は発達途中だからこそ、今のケアが将来の健康を左右します。
以下のような対策が効果的です。
家庭でできる工夫
- はだしで遊ぶ時間をつくる
- バランスボールやトランポリン遊び
- 足指を使う遊び(タオルつかみゲームなど)
- 足に合った靴を選ぶ
柔道整復師・鍼灸師監修コメント
子どもの足のトラブルは、「成長すれば自然に治る」と放置されがちですが、“今”の体の使い方が将来の成長に直結します。足裏アーチが不安定なまま成長すると、膝や腰の痛み・姿勢不良につながることもあります。姿勢や歩き方、バランス感覚を見直すことは、体幹や集中力の育成にもつながります。
お子さまの足の不調、「成長だから」と見過ごさずに
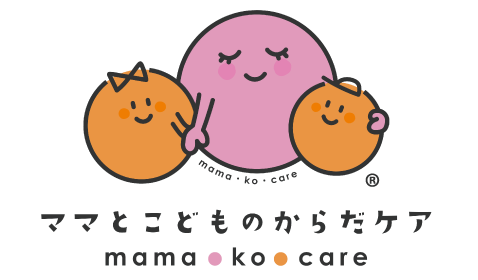
「疲れやすい」「転びやすい」といった症状は、成長過程で起こりやすいからこそ早めの対処がカギです。ママこケアでは、子どもの成長に寄り添いながら足や姿勢をサポートする治療院をご紹介しています。
※治療内容・方針は院によって異なります。詳しくは各院にご確認ください。
足に関するよくある質問
①かかとがしっかりしていること、
②つま先に適度な余裕があること、
③足首や甲が安定するベルトや紐があること、
④インソールのアーチサポートが適度なもの、
を意識しましょう。歩きやすさと安定性のバランスが重要です。