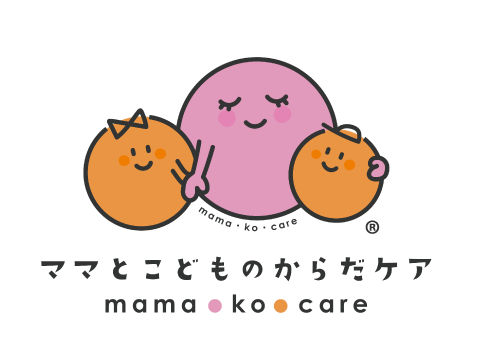目次
COLUMN
産後の頭痛がつらい…ホルモン変化と姿勢の意外な関係とは?
「産後から頭痛が増えた気がする」
赤ちゃんのお世話や家事に追われながら、ふとした時に感じる“ズキズキ”“締め付け”――
それ、産後特有の頭痛かもしれません。
実はこの時期の頭痛には、ホルモンの急変・姿勢のゆがみ・自律神経の乱れ・血流障害など、いくつもの要素が複雑に絡み合って起きていることが多くあります。単なる「育児疲れ」や「寝不足」で片づけず、体の声に目を向けてみましょう。
産後頭痛の主な原因とは?
1. ホルモンバランスの劇的変化
出産後、女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)は一気に低下。このホルモンの急激な変化は、脳の視床下部や下垂体を介して自律神経にも大きな影響を与えます。
→ 自律神経の乱れは血管の拡張・収縮に影響し、「片頭痛」や「緊張型頭痛」の発生リスクを高めます。
2. 姿勢の乱れと筋緊張
授乳、抱っこ、沐浴、寝かしつけ…産後のママは前かがみ・猫背・巻き肩など、肩・首・背中に負担のかかる姿勢が続きがち。
- 頚部の後屈(首の反らし)
- 頭部前方変位(ストレートネック)
- 肩甲帯の固定による肩こり
これらの姿勢不良により、後頭部〜首の筋緊張が持続→筋緊張性頭痛を引き起こすケースがよく見られます。
3. 自律神経と血流のアンバランス
ホルモンだけでなく、夜間授乳による睡眠不足や育児ストレスも交感神経の過剰優位を招き、頭痛の悪化につながります。また、ストレスによって顎を食いしばるクセが強くなると、側頭筋・咬筋の過緊張→頭部への緊張性負荷が強まります。
4. 水分・栄養不足、低血糖
産後は水分補給や食事のリズムも乱れがちです。授乳による脱水や鉄分不足、低血糖は脳の血管に直接影響し、頭痛を誘発することがあります。
どのタイプの頭痛?自分の頭痛を知ろう
| 頭痛のタイプ | 特徴 | 原因 |
|---|---|---|
| 緊張型頭痛 | 頭を締め付けられるような鈍い痛み | 首・肩などの筋緊張 |
| 片頭痛 | 脈打つようなズキズキとした痛み、片側に多い | 血管拡張・ホルモン変化 |
| 群発頭痛 | 一定期間に集中して起きる激痛 | 血管性・自律神経の異常 |
自分でできる産後頭痛のセルフケア
朝日を浴びてホルモンリズムを整える
体内時計をリセットするために、朝はカーテンを開けて日光を浴びるのが効果的。セロトニン分泌が促され、自律神経が安定します。
首・肩・肩甲骨まわりのケア
簡単なストレッチや温熱で、僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋をリリースしましょう。また、胸の筋肉(大胸筋)のストレッチも、巻き肩改善に有効です。
湯船につかる
38~40℃のぬるめのお湯で15分程度入浴することで、副交感神経が優位に。冷え性のあるママは足湯や首元を温めるのもおすすめです。
栄養を意識した食事
鉄分(赤身肉・レバー)、マグネシウム(ナッツ・海藻)、ビタミンB群(豚肉・卵)を意識的に取り入れて神経系と血流をサポート。
柔道整復師・鍼灸師監修コメント
産後の頭痛は、単一の原因ではなく「ホルモン・筋肉・神経・生活リズム」が複雑に影響しています。治療現場では、姿勢評価・動作確認・ストレス状況など多角的に見立てることで、根本改善につなげています。我慢せず、ぜひ専門家に相談を。
ママの不調は、家庭全体の笑顔を左右する
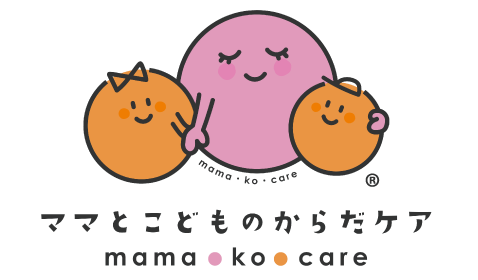
育児は24時間休みなし。ママ自身が「自分の不調を後回し」にしがちですが、まずは自分のケアを大切にすることが、家族の健康と安心につながります。
「つらさをわかってくれる人に話したい」「薬に頼らず自然に整えたい」――そんなときは、ママケアに強い専門家のサポートを受けてみてください。
※治療内容・方針は院ごとに異なります。詳細は各院にご確認ください。