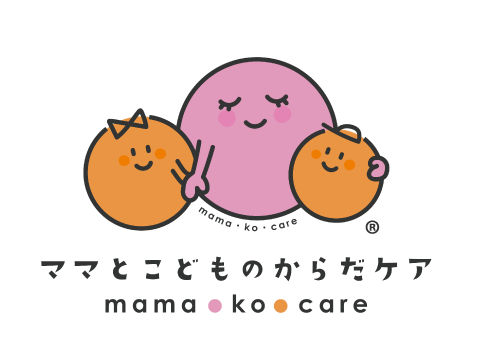目次
COLUMN
「運動すると膝が痛い…」成長痛(オスグッド)の正しいケアとは?
成長期の子どもに多い“ひざの痛み”の原因と対処法
- 「練習後に膝が痛いと泣く」
- 「正座ができない」
- 「膝のお皿の下が腫れてきた」
――そんな悩み、ありませんか?
活発に運動している小・中学生の子どもに多いのが、「成長痛」とも呼ばれるオスグッド病(オスグッド・シュラッター病)です。この記事では、オスグッドの原因や見分け方、セルフケアのポイント、さらに他の部位に出る“成長痛”についても分かりやすく解説します。
オスグッド病ってなに?
オスグッド病とは、成長期の子どもの「膝のお皿の下」に痛みや腫れが出るスポーツ障害の一つです。特に、ジャンプやダッシュ、しゃがむ動作が多いスポーツ(サッカー・バスケ・バレー・野球など)をしている10〜15歳の男子に多く見られます。
原因は“成長期ならでは”の骨と筋肉のアンバランス。成長期の子どもは、骨が急速に伸びていくのに対して、筋肉や腱の柔軟性が追いつかない状態にあります。この状態で運動を続けると、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が硬くなり、膝下の骨(脛骨粗面)を強く引っぱることで炎症が起こるのです。
オスグッドの主な症状
- 膝下(お皿の下)が腫れて出っ張る
- 押すと痛い
- 正座や階段の上り下りがつらい
- ジャンプ・ダッシュ時に激痛
- 両膝より片膝に出やすい
放置すると痛みが長引いたり、運動を続けることが難しくなることもあります。
成長痛=安静?それだけじゃないケアのポイント
「痛みがあるなら運動を休ませよう」と思いがちですが、ただの安静だけでは根本的な解決にならないことも。成長痛に対しては、次のようなケアが有効です。
筋肉の柔軟性を高める
太ももの前側(大腿四頭筋)やお尻、ふくらはぎのストレッチで、膝にかかる負担を軽減します。
アイシング・炎症ケア
運動後や痛みが強いときは、膝周囲を10〜15分冷やすことで炎症を抑えましょう。
姿勢・体の使い方を見直す
猫背や反り腰、膝を内側に入れるクセがあると、オスグッドを悪化させやすくなります。接骨院や鍼灸院での姿勢評価や施術が有効です。
運動量の調整と休息のバランス
完全に運動をやめる必要はありませんが、痛みが強い時期はメニューの見直しや休息を取り入れましょう。
他にもある、成長期の子どもの“痛み”
オスグッド以外にも、成長期にはさまざまな部位に痛みが現れることがあります。
セーバー病(かかとの痛み)
ジャンプや走行動作で、踵の骨に負荷がかかり発症。小学生の男の子に多く、サッカーや陸上競技で見られます。
腰椎分離症(腰の痛み)
成長期に激しいスポーツをしていると、腰椎(腰の骨)に負荷がかかり疲労骨折することがあります。
シンスプリント(すねの内側の痛み)
ランニング中心のスポーツ(陸上・バスケなど)に多く、すねの骨膜に炎症が起こる状態です。
柔道整復師・鍼灸師監修コメント
成長痛は「成長期だから仕方ない」と思われがちですが、体の使い方や筋肉のアンバランスが背景にあるケースがほとんどです。
施術では、炎症を抑えるケアに加え、姿勢や筋力バランスを整えるアプローチを行います。放置せず、早期に専門家へ相談することをおすすめします。
「我慢せず、ケアすることが未来のパフォーマンスに」
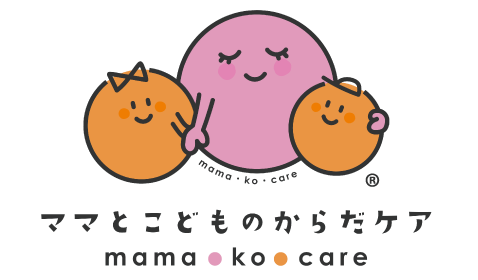
「試合が近いから」「みんな痛いって言ってるし」――そんな理由で我慢してしまう子どもも少なくありません。
しかし、成長痛は正しくケアすることで回復しやすく、再発も防げます。ママこケアでは、子どもの成長痛に対応した治療院を紹介しています。「運動を続けながらケアしたい」「本人の体の状態をしっかり見てほしい」そんな時は、お気軽にご相談ください。
※治療内容・方針は院ごとに異なります。詳細は各院にご確認ください。