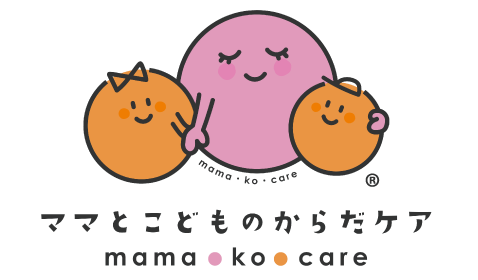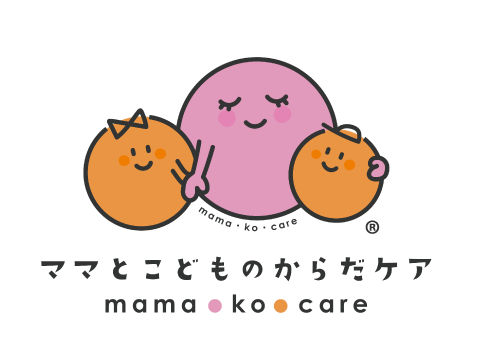「なんだか毎日だるい」その不調、“気象病”かもしれません
季節の変わり目や梅雨時期に、「頭が重い」「肩こりがひどい」「朝からだるくてやる気が出ない」――そんな不調を感じるママは少なくありません。
病院に行くほどではないけれど、いつもと違う不調が続く…それは、気象病(天気痛)と呼ばれる、気圧や湿度、気温の変化が体に影響する不調かもしれません。
気象病ってなに?どうしてママに多いの?
「気象病」とは、気圧や天候の変化によって自律神経が乱れ、体にさまざまな症状が現れる状態を指します。特に産後や育児中のママは、ホルモンバランスや睡眠リズムの乱れ、疲労の蓄積により、もともと自律神経が敏感になりやすい時期です。
よくある気象病の症状
- 頭痛・めまい・肩こり
- 全身のだるさ・疲労感
- 気分の落ち込み・イライラ
- 吐き気・耳鳴り
- 関節の痛みや冷え
自律神経と体の不調の関係
自律神経は「交感神経(活動)」と「副交感神経(休息)」のバランスで体をコントロールしています。気圧が急に下がると、内耳にある気圧センサーが過剰に反応し、交感神経が刺激されます。その結果、血管が収縮して頭痛が起きたり、筋肉がこわばって肩こりや倦怠感が出たりするのです。
忙しいママでもできる!気象病セルフケア
朝日を浴びて“体内時計”をリセット
朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びましょう。体内時計が整い、自律神経のリズムが安定します。
首・肩まわりのストレッチ
気圧の影響を受けやすい首・肩の血流を良くすることで、頭痛やだるさを予防できます。
湯船にゆっくり浸かる
38~40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、副交感神経が優位になりリラックスできます。
食事で「鉄分・たんぱく質・ビタミンB群」を意識
神経系や血流の働きを助ける栄養素を意識的に摂取することで、不調に強い体づくりをサポートします。
気圧変化アプリで“予測”して行動
天気アプリで気圧の変化を把握しておくと、事前に対策しやすくなります。
柔道整復師・鍼灸師監修コメント
季節の変わり目は体のバランスが崩れやすく、気象の変化に自律神経が過敏に反応することがあります。鍼灸や整体では、首肩周りや自律神経に関わる経絡へのアプローチにより、自然治癒力を高め、症状の緩和を図ることが可能です。放っておかず、早めのケアが大切です。
つらいときは、無理せず専門家に相談を
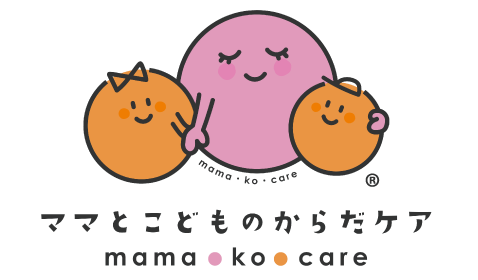
「毎年梅雨になると不調になる」「育児中で対策する余裕がない」そんな時は、専門の治療院で体質や生活リズムに合ったサポートを受けるのも一つの選択肢です。ママこケアでは、育児中のママに寄り添った施術を提供している治療院を紹介しています。ご自身に合ったケア方法を見つけるきっかけに、ぜひご活用ください。
※店舗ごとにサポート内容や対応方針は異なるため、詳しくは各院へ直接ご確認ください。
気象病に関するよくある質問
Q1:気圧の変化に敏感な体質は遺伝しますか?
A1:遺伝の可能性は一部で示唆されていますが、生活習慣が大きく関わります。親が天気の変化に弱いと、子どもも自律神経が敏感な傾向を持つことがあります。とはいえ、毎日の睡眠・食事・運動といった基本的な生活リズムを整えることで、体質の影響は軽減できます。特に成長期の子どもは環境に影響されやすいため、家庭でのサポートが重要です。
Q2:気象病による頭痛と片頭痛の違いは何ですか?
A2:気象病は鈍く重い痛み、片頭痛はズキズキと脈打つ痛みが特徴です。気象病では気圧低下のタイミングでだるさや眠気、肩こりを伴う頭痛が出やすく、片頭痛では光や音への過敏、吐き気を伴うこともあります。どちらも生活に支障をきたすため、原因を見極めて対策をとることが大切です。
Q3:気象病はいつの季節に多くなりますか?
A3:梅雨・秋の台風シーズン・春の寒暖差が大きい時期に増加傾向があります。特に6月〜7月の湿気と気圧変動が激しい梅雨時期や、9月〜10月の台風・気温変化がある時期は、気象病の症状が出やすいです。この時期は「天気痛」とも呼ばれ、だるさや頭痛、関節の痛みを訴える人が増加します。
Q4:気象病に悩む子どもも増えていますか?
A4:はい。とくに小学校高学年〜中学生にかけて、体調不良を訴える例が増えています。成長期の子どもは、自律神経が未熟で気圧や気温の変化に影響されやすい傾向があります。「朝起きられない」「頭が重い」「食欲がない」などの訴えが続く場合は、生活リズムと共に、自律神経のケアが求められます。
Q5:気象病を予防する食事のポイントはありますか?
A5:自律神経を整える栄養素(ビタミンB群、マグネシウム、鉄分)を意識しましょう。温かいみそ汁、野菜たっぷりのスープ、良質なタンパク質(卵・魚・納豆など)を日常に取り入れることで、体を内側から整えます。また、冷たい飲み物や甘いものの摂りすぎは、内臓を冷やし自律神経の働きを乱すため注意が必要です。
Q6:授乳中や妊娠中でも気象病になりますか?
A6:なります。ホルモンバランスが乱れやすい時期なので、より影響を受けやすいです。妊娠・授乳期はホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の変動に加え、睡眠不足や姿勢の乱れも重なります。気圧の影響を受けやすく、めまいや倦怠感、頭痛を感じやすくなるため、無理をせず生活習慣を整えることが大切です。
Q7:更年期と気象病の違いは?
A7:症状は似ていますが、原因が異なります。更年期は女性ホルモン(エストロゲン)の低下によって起きる体の不調で、ホットフラッシュ・冷え・イライラなどが特徴です。気象病は気圧や気温変化による自律神経の乱れが原因です。両者は併発することもあるため、正確な判断と対応が求められます。
Q8:市販薬で気象病の症状は改善しますか?
A8:鎮痛薬などで一時的に症状を和らげることは可能ですが、根本改善にはなりません。気象病の本質は自律神経の乱れにあるため、生活リズムの見直しや睡眠・栄養・運動といった総合的なケアが必要です。薬に頼りすぎず、体質を整えるアプローチが理想です。
Q9:天気痛と気象病は同じ意味ですか?
A9:基本的には同じですが、使われる場面に違いがあります。「天気痛」は頭痛や関節痛など痛みを主とした症状に対して使われることが多く、「気象病」はだるさ・疲労感・眠気・めまいといった幅広い体調不良を含む言葉です。どちらも天候変化が誘因であることに変わりありません。
Q10:気象病におすすめの漢方や東洋医学のケアは?
A10:五苓散・苓桂朮甘湯などが代表的で、冷え・めまい・むくみに対応します。東洋医学では、気・血・水のバランスを整えることで自律神経の不調を改善すると考えます。冷え体質、水分代謝の悪いタイプ、ストレスを溜め込みやすいタイプなど、体質ごとにケアの方法が異なるため、専門家の判断を仰ぐのが安心です。